なぜ乳幼児の睡眠を整えることが大切なのか
お子さんの寝かしつけ、毎日おつかれさまです!私も子どもが生まれたばかりの頃は、なかなか寝てくれなくて困り果てていました。
実は、乳幼児期の睡眠って、単に「今日眠れるかどうか」の問題じゃないんですよね。最近の研究では、規則正しい睡眠習慣が社会性の発達や認知機能の向上と関連していることが分かってきています。
大阪大学の研究チームが発表した論文では、睡眠時間のばらつきが大きい子どもは人を見る割合が少なく、睡眠時間が短い子は脳活動に変化があることが確認されました。つまり、規則的な睡眠は子どもの脳の発達にとって本当に大切なんです!
でも、だからといって完璧を目指す必要はありません。私たち親にできるのは、子どもが自然と眠りやすい環境を整えてあげることだと思います。今回は、研究に基づいた「再現性の高い」睡眠の整え方を3つのステップでお伝えしますね。
ステップ1:睡眠環境を整える
温度と湿度の管理
赤ちゃんが眠る部屋の環境、意外と見落としがちですよね。私も最初は「なんとなく快適」で済ませていたんですが、数値で管理するようになってから格段に寝つきが良くなりました!
理想的な室温は季節によって異なります。冬場は20〜22℃、夏場は28℃くらいを目安にしてみてください。湿度は年間を通して40〜60%がベストです。エアコンの設定温度だけでなく、赤ちゃんの寝ている場所の実際の温度を測ることが大切なんですよ。
床に近い場所と天井付近では温度が違うことも多いので、
を枕元に置いておくと安心です。私も使っていますが、これがあるだけで「暑すぎないかな」「寒くないかな」という不安がぐっと減りました。
照明のコントロール
光の管理も睡眠リズムを作る上でとっても重要なポイントなんです。赤ちゃんの体内時計は、光の刺激によって調整されていくんですよ。
昼間のお昼寝時は「晴れた日の公園の木陰」くらいの明るさが理想的だと言われています。カーテンはレースのものだけにして、ほどよく明るさを保ちましょう。真っ暗にすると昼夜の区別がつきにくくなるので、むしろ避けたほうがいいですね。
夜は逆に、できるだけ暗い環境を作ってあげてください。常夜灯を使う場合も、赤ちゃんの目に直接光が入らない位置に置くことが大切です。電球色の間接照明なら、夜中の授乳やおむつ替えの時も赤ちゃんを起こしすぎずに済みますよ。
ステップ2:時刻を固定する
朝の起床時刻が最優先
生活リズムを整える時、実は「何時に寝かせるか」よりも「何時に起こすか」の方が重要なんです!これは私も知った時に目からウロコでした。
毎朝7〜8時の間の決まった時間に起こすことで、夜に眠くなる時間も自然と定まってきます。前日に遅く寝てしまった日も、できるだけいつもの時間に起こしてあげてください。最初は辛いかもしれませんが、数日続けるとリズムが整ってくるはずです。
就寝時刻の目安
専門家の研究によると、乳幼児の健やかな成長のためには、夜7時から朝7時の間に9〜11時間の持続した睡眠が必要だとされています。朝7時に起きる生活を考えると、夜8〜9時までには寝かせたいところですね。
とはいえ、現実には家庭の事情もありますよね。大切なのは「毎日同じ時間に寝て起きる」ということ。入眠・起床時刻のばらつきが前後30分以内に収まるように意識してみてください。体内時計は2歳頃までにほぼ完成すると言われているので、この時期に規則的なリズムを作ることが生涯の健康につながるんです。
ステップ3:刺激をコントロールする
昼間はしっかり刺激を
夜ぐっすり眠ってもらうためには、昼間の過ごし方も大切なんですよ。日中は明るい環境で、たくさん遊んだり外の空気を吸ったりして、適度に疲れさせてあげましょう。
朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされます。散歩や外遊びの時間を作れるといいですね。私の経験では、午前中に15分でも外に出ると、その日のお昼寝も夜の寝つきも全然違いました!
夜は静かにトーンダウン
夕方から夜にかけては、徐々に刺激を減らしていく時間です。テレビやスマホの画面は寝る1時間前くらいから避けたいところですね。ブルーライトが体内時計を乱してしまうので、これは大人にも当てはまります。
照明も段階的に暗くしていきましょう。夕食後はリビングの明かりを少し落として、お風呂、絵本の読み聞かせ、子守唄といった「眠りのルーティン」を作ってあげるといいですよ。
入眠儀式を作る
「この流れが来たら寝る時間だ」と赤ちゃんが理解できるように、毎日同じ順序で寝かしつけをすることが効果的です。例えば「お風呂→授乳→子守唄→寝室へ」というような流れですね。
うちでは、お風呂の後に部屋の照明を落とすボタンを子どもに押させていました。子どもってスイッチが好きなので、喜んで自分から暗くしてくれるんですよ!こういう小さな工夫が、スムーズな寝かしつけにつながります。
完璧を目指さなくていい
ここまで3つのステップをお伝えしましたが、すべてを完璧にこなす必要はありません。私も毎日理想通りにはいきませんし、それでいいんだと思います。
大切なのは、できることから少しずつ取り入れていくこと。環境を整えて、時刻を意識して、刺激をコントロールする。この3つの軸を意識するだけでも、睡眠の質は変わってくるはずです。
赤ちゃんの睡眠には個人差もありますし、発達段階によっても変化します。うまくいかない日があっても、自分を責めないでくださいね。焦らず、お子さんのペースを大切にしながら、一緒に良い睡眠習慣を作っていきましょう!
参考資料
- 幼児期早期の規則正しい睡眠が社会性発達や脳機能と関連する – 大阪大学
- 子どもの睡眠科学 – くらしスタイル研究所
- 乳幼児期の睡眠リズムの発達 – CiNii Research
- 新生児と乳児の睡眠 – MSDマニュアル
- 赤ちゃんが眠る部屋の温度の目安 – パンパース
- 0~2歳児の子を持つ親への調査結果 – 江崎グリコ
関連記事

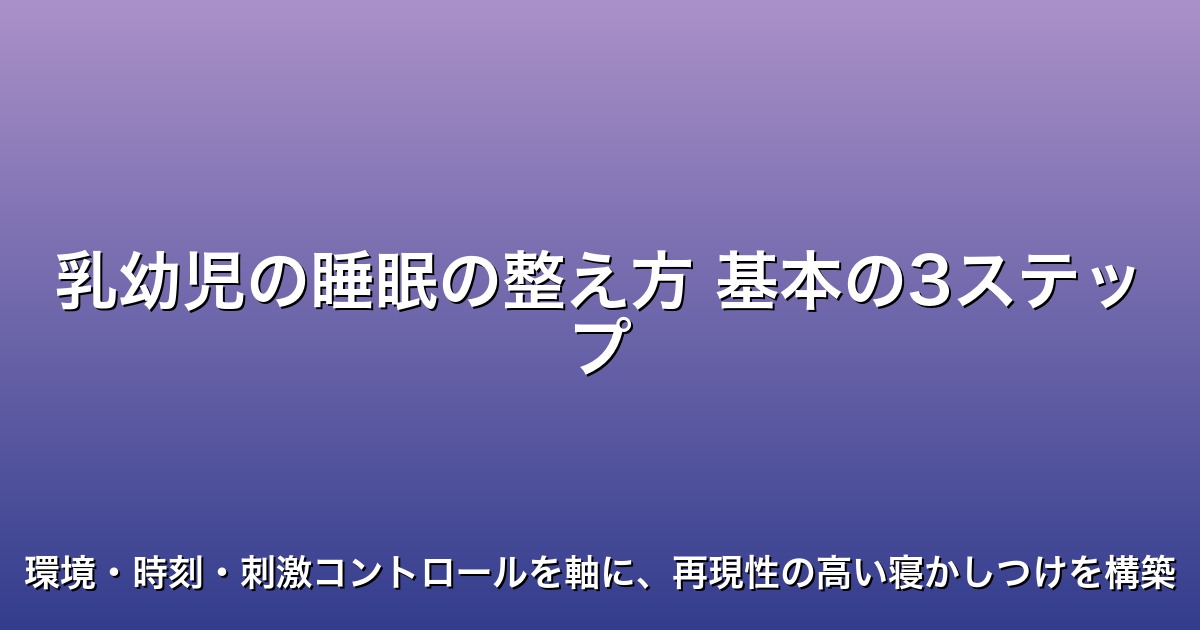


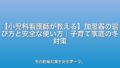
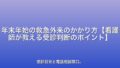
コメント