年末年始の救急外来、いつ受診すべき?
年末年始って、かかりつけの小児科がお休みで不安になりますよね!うちも去年の年末、子どもが夜中に急に熱を出して焦りました。救急外来に行くべきか、朝まで様子を見るべきか、本当に迷うんです。
小児科で働いていると、年末年始の救急外来は本当に混み合うのを目の当たりにします。でも同時に、「これは朝まで待てたかも…」というケースも正直あるんですよね。だからこそ、受診の目安を知っておくことが大事なんです。
今回は看護師として、そして子育て中の親として、年末年始の救急外来のかかり方を実体験も交えてお伝えしていきます。いざという時に慌てないための準備、一緒に確認していきましょう!
すぐに救急外来を受診すべき症状
迷わず119番!命に関わる緊急症状
まず最初に、救急車を呼ぶべき症状をしっかり覚えておいてください。日本小児科学会のガイドラインでも、以下の症状は緊急対応が必要とされています(1)。
- 呼吸が苦しそうで、肩で息をしている
- 唇や顔色が紫色や真っ青になっている
- けいれんが5分以上続いている、または繰り返している
- 意識がもうろうとしている、呼びかけても反応が鈍い
- 生後3ヶ月未満で38度以上の発熱がある
- 激しい嘔吐や下痢で、ぐったりして水分が取れない
- 頭を強く打って、嘔吐やけいれんがある
これらの症状があったら、ためらわず119番してください!「こんなことで救急車を呼んでいいのかな」って躊躇する気持ち、すごく分かります。でも命に関わる可能性があるときは、遠慮する必要はないんです。
車で救急外来へ!夜間でも受診を考える症状
119番ほどではないけれど、朝まで待てない症状もあります。厚生労働省の「こどもの救急」サイトでは、以下のような場合は夜間でも受診を検討するよう推奨されています(2)。
- 38度以上の熱があり、水分が取れず尿が6時間以上出ていない
- 激しい腹痛が続いている
- 嘔吐が止まらず、水分も受け付けない
- 3ヶ月以上で40度以上の高熱がある
- けいれん後、意識が戻っているが元気がない
- 呼吸がいつもより速く、苦しそう
ただし、これらの症状でも「迷ったらまず電話相談」が基本です。次のセクションで詳しく説明しますね!
受診前に必ず使いたい!電話相談窓口
#8000(小児救急電話相談)は年末年始も対応
救急外来に行く前に、ぜひ活用してほしいのが「#8000」です!これは厚生労働省が実施している小児救急電話相談事業で、看護師や小児科医が電話で相談に乗ってくれるんです(3)。
うちも何度もお世話になりました。夜中に子どもが熱を出したとき、「今すぐ受診が必要か、朝まで様子を見ていいか」を判断してもらえるんですよね。年末年始も基本的に対応していますが、都道府県によって実施時間が違うので確認が必要です。
電話では以下のことを聞かれることが多いので、あらかじめメモしておくとスムーズですよ!
- 子どもの年齢と体重
- いつから、どんな症状があるか
- 体温は何度か(測定時刻も)
- 水分や食事は取れているか
- おしっこは出ているか
- 持病やアレルギーはあるか
その他の相談窓口も覚えておこう
#7119(救急安心センター)も便利な窓口です。大人の症状にも対応していて、「救急車を呼ぶべきか」「今すぐ病院に行くべきか」を相談できます。ただし実施していない地域もあるので、事前に確認しておくといいでしょう(4)。
また、中毒110番(大阪:072-727-2499、つくば:029-852-9999)は、誤飲事故の際に専門的なアドバイスがもらえます。年末年始も対応しているので、番号を控えておくと安心ですね!
救急外来を受診する前の準備
持っていくべきもの5点セット
救急外来に行くときは、以下のものを忘れずに持っていきましょう。慌てていると忘れがちなので、普段から救急セットとしてまとめておくのがおすすめです!
- 健康保険証・医療証(乳幼児医療証など)
- 母子健康手帳(予防接種歴の確認に必要)
- お薬手帳(現在飲んでいる薬がある場合)
- 体温計の記録(いつから何度あったか)
- 現金やクレジットカード(時間外は現金のみの場合も)
うちでは玄関近くに「救急セット」を置いています。保険証のコピーや現金、子どもの着替えなどを入れたポーチです。いざという時、これを持っていけばOKなので焦らずに済むんですよね!
症状の経過をメモしておく
医師に症状を正確に伝えるために、時系列でメモしておくと診察がスムーズです。特に以下の情報は重要ですね。
- 症状が始まった日時
- 体温の変化(測定時刻と温度)
- 嘔吐や下痢の回数
- 水分や食事の摂取状況
- おしっこの回数と量
- 家で試した対処法
スマホのメモ機能を使うと便利ですよ。写真で記録するのもいいと思います!
年末年始特有の注意点
救急外来の混雑を覚悟する
年末年始の救急外来は、通常の3〜5倍混み合うことも珍しくありません。小児科の救急外来は特に混雑するんですよね。待ち時間が2〜3時間になることも覚悟しておいてください。
待っている間に症状が悪化する可能性もあるので、待合室で子どもの様子をよく観察することが大事です。ぐったりしてきたり、呼吸が苦しそうになったりしたら、すぐに受付に伝えましょう!
処方薬が限られる場合がある
年末年始は院内薬局しか対応していないことが多く、普段使っている薬がない場合もあります。また、休日加算で医療費が高くなることも覚えておいてください。
持病があって定期的に薬を飲んでいる子どもの場合は、年末までに必要な分を処方してもらっておくのがおすすめですね。うちもかかりつけ医に相談して、年末に多めに処方してもらうようにしています!
帰省先での医療機関を事前に調べる
実家に帰省する場合は、事前に近くの救急医療機関を調べておきましょう。各都道府県の「医療情報ネット」や「救急医療情報センター」で、年末年始に対応している病院を検索できます(5)。
スマホに住所と電話番号を登録しておくと、いざという時に慌てずに済みますよ!
家庭でできる対応と様子見のポイント
発熱時の基本ケア
38度以上の熱があっても、水分が取れて機嫌が良ければ、朝まで様子を見ても大丈夫なことが多いんです。日本小児科学会のガイドラインでも、熱だけで慌てて受診する必要はないとされています(6)。
家庭でできる基本ケアは以下の通りです。
- 水分をこまめに取らせる(経口補水液やイオン飲料)
- 薄着にして、室温は20〜22度くらいに保つ
- 寒気がある時は温かくして、熱が上がりきったら薄着に
- 解熱剤は38.5度以上で辛そうな時に使用
ただし、生後3ヶ月未満の赤ちゃんの発熱は、必ず受診が必要です。これは絶対に覚えておいてください!
嘔吐・下痢の時の水分補給
嘔吐や下痢がある時は、脱水が心配ですよね。でも一気に水分を取らせると、また吐いてしまうんです。日本小児救急医学会の推奨では、少量ずつ頻回に与えるのが基本とされています(7)。
うちでは5〜10分おきに、スプーン1杯ずつ飲ませるようにしています。経口補水液が理想的ですが、嫌がる場合は薄めたリンゴジュースでもOKですよ。
救急外来を受診する時のマナー
トリアージを理解する
救急外来では、来た順番ではなく「緊急度」の高い順に診察します。これをトリアージと言うんですよね。だから先に来たのに後から来た人が先に呼ばれることもあるんです。
「なんでうちが後なの!」って思う気持ちも分かります。でも、もし自分の子どもが重症だったら、優先的に診てほしいですよね。お互い様の精神が大事だと思います!
感染症対策を忘れずに
救急外来には色々な症状の患者さんが集まります。可能であればマスクを着用し、他の患者さんとの距離を保つようにしましょう。
嘔吐物や下痢便で汚れたものは、ビニール袋に密閉して持ち帰るのがマナーですね。ウイルス性の感染症の可能性もあるので、感染拡大を防ぐ意識が大切です!
まとめ:事前準備と冷静な判断が大切
年末年始の救急外来、いかがでしたか?看護師として働いていると、「もう少し早く相談してくれれば」「これは朝まで待てたかも」と思うケースを本当に多く見るんです。
でも親としての気持ちもすごく分かります!特に初めての子育てだと、どんな症状でも心配になりますよね。だからこそ、#8000のような相談窓口を活用してほしいんです。専門家に相談するだけでも、気持ちが落ち着くことがありますから。
大事なのは、事前の準備と冷静な判断です。救急セットを用意しておく、相談窓口の番号を登録しておく、受診の目安を知っておく。これだけでも、いざという時の安心感が全然違うと思います。
年末年始も、お子さんが元気に過ごせますように。でももし何かあっても、この記事が少しでも役立てば嬉しいです。一緒に乗り切りましょうね!
関連記事(内部リンク候補)
- 子どもの発熱、受診の目安と家庭でのケア方法
- 冬に流行する感染症と予防対策
- 嘔吐下痢症の対処法と脱水のサイン
- 子どもの誤飲事故、応急処置と予防策
- 小児科の上手なかかり方と準備するもの
参考資料
- 日本小児科学会 こどもの救急
- 厚生労働省 小児救急電話相談事業(#8000)について
- 日本小児救急医学会 小児の救急対応ガイドライン
- 総務省消防庁 救急安心センター事業(#7119)
- 厚生労働省 医療情報ネット
関連記事

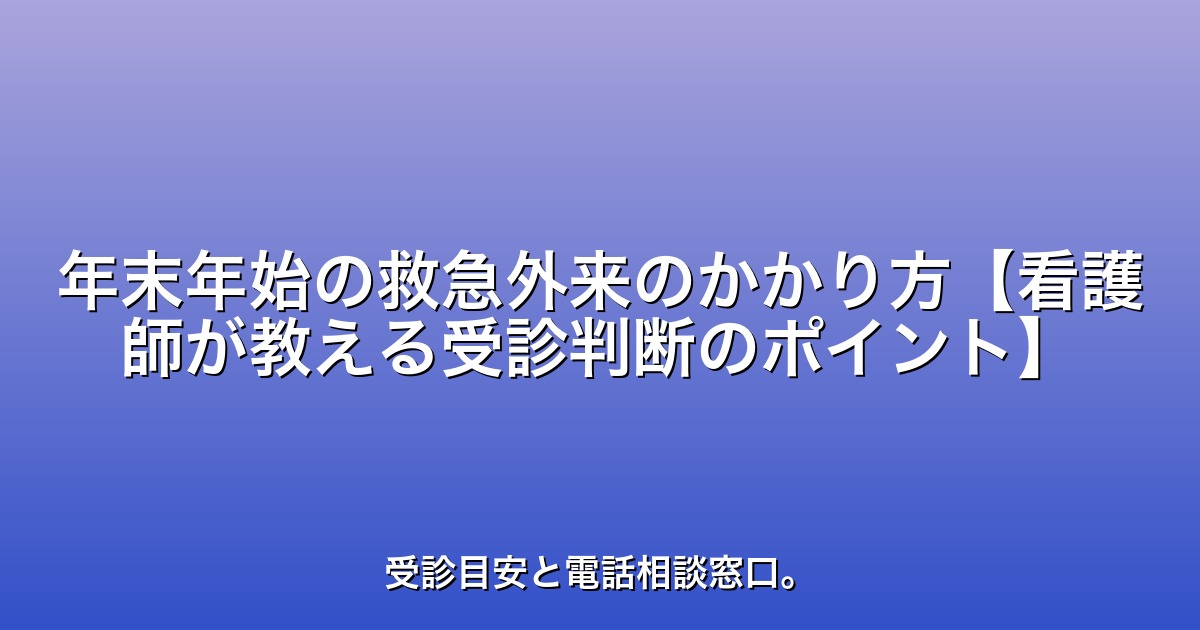

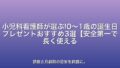
コメント