子どもの突然の嘔吐、慌てないために
深夜に突然「ママ…気持ち悪い」と言われて、慌てて駆けつけたら床一面に…なんて経験、ありませんか?私も看護師として、そして親として何度も経験してきました。
感染性胃腸炎の季節になると、本当にドキッとしますよね。でも、正しい処理方法を知っていれば、家族内での感染を最小限に抑えられるんです!
今回は、吐物や下痢の処理で大切な「塩素消毒の濃度」と「具体的な手順」をまとめました。慌てているときこそ、この記事を見返してもらえたら嬉しいです。
まず知っておきたい!塩素濃度の違い
ノロウイルスなどの感染性胃腸炎に効果があるのは、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)です。アルコール消毒では不十分なのがやっかいなところなんですね。
処理する場所によって濃度を使い分けるのがポイントです。濃すぎても薄すぎても困るので、ここはしっかり確認しておきましょう!
場所別・塩素濃度の早見表
【0.1%(1000ppm)】吐物や便がついた場所
- 床に吐いた吐物の処理
- 便がついたトイレの便座
- 汚物がついた衣類やシーツ
【0.02%(200ppm)】吐物がない場所の予防消毒
- トイレのドアノブ
- 手すり・スイッチ
- 洗面所の蛇口
- おもちゃ・リモコン
- 食器類
家庭用漂白剤での作り方(濃度6%の場合)
一般的な家庭用塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)は約6%濃度です。ペットボトルのキャップ1杯が約5mlなので、これを目安にすると簡単ですよ。
0.1%消毒液(吐物処理用)
- 水500ml+漂白剤キャップ2杯(10ml)
- または水1L+漂白剤キャップ4杯(20ml)
0.02%消毒液(ドアノブなど)
- 水500ml+漂白剤キャップ約1杯弱(2ml)
- または水1L+漂白剤キャップ約1杯弱(4ml)
消毒液は光や熱で分解してしまうので、使う直前に作るのが鉄則です!作り置きは効果が落ちてしまうんですね。透明容器だと24時間で濃度が大きく低下するというデータもあるそうです。
吐物処理の具体的な手順
実際に吐物を処理するときは、二次感染を防ぐことが最優先です。慌てる気持ちはわかりますが、まず自分を守る装備からスタートしましょう。
準備するもの
- 使い捨てマスク
- 使い捨て手袋(二重にすると安心)
- 使い捨てエプロンまたはゴミ袋で代用
- ペーパータオルや新聞紙
- ビニール袋(2枚以上)
- 0.1%塩素系消毒液
- バケツ
我が家では「吐物処理セット」として、これらをまとめて押入れに常備しています。夜中に慌てて探すのは本当に大変なので、おすすめですよ!
処理の手順(6ステップ)
1. まず換気!
窓を開けて、家族を別の部屋に移動させます。ノロウイルスは乾燥すると空気中に舞うので、換気は本当に大切なんです。
2. 装備を整える
マスク、手袋、エプロンを装着。髪が長い人はまとめておきましょう。
3. 吐物を取り除く
ペーパータオルや新聞紙で、外側から内側へ静かに拭き取ります。飛び散らせないように、そっと包み込む感じがコツです。取り除いたものはすぐにビニール袋へ。
4. 0.1%消毒液で消毒
吐物があった場所より広めの範囲に、消毒液を染み込ませたペーパータオルを置きます。スプレーすると飛沫が舞うので、浸すように拭くのがポイントなんですね。
5. 10分以上放置
この待ち時間が大事!すぐに拭き取ってしまうと、ウイルスが残ってしまいます。
6. 仕上げ拭き
時間が経ったら、水拭きして完了です。金属部分を消毒した場合は、腐食防止のためにしっかり水拭きしてくださいね。
使用した手袋やマスク、ペーパータオルは、すべてビニール袋に入れて密閉してから捨てます。作業後は石鹸でしっかり手洗いを!
洗濯のポイント|普段と同じではダメなんです
吐物や下痢便がついた衣類、そのまま洗濯機に入れちゃダメ!って知っていましたか?実は通常の洗剤では、ノロウイルスは死滅しないんです。
汚れた衣類の洗濯手順
ステップ1:下処理
まず固形物を取り除いてから、水(お湯ではない!)でもみ洗い。タンパク質が含まれているので、いきなり熱いお湯を使うと固まってしまうんですね。バケツの中で静かに洗いましょう。
ステップ2:消毒(2つの方法から選択)
- 方法A:塩素系漂白剤 0.02%の消毒液に30分〜1時間浸す(白い衣類向け。色柄物は色落ちする可能性があります)
- 方法B:熱湯消毒 85℃以上のお湯に1分以上浸す(色柄物にはこちら!煮沸やスチームアイロンでもOK)
ステップ3:洗濯
消毒後、洗濯機で通常通り洗います。ただし、他の家族の洗濯物とは分けて洗うのが安心です。可能なら高温乾燥機を使うと、さらに効果的ですよ。
スチームアイロンは我が家でも重宝しています。布団やぬいぐるみなど洗えないものにも使えるので便利なんです!
洗濯機の消毒も忘れずに
汚れた衣類を洗った後の洗濯機も、実は心配ですよね。洗濯槽洗浄モードがあれば、塩素系の洗濯槽クリーナーを使って洗浄しておくと安心です。
トイレ・洗面所の予防消毒
家族が感染性胃腸炎にかかったら、毎日の予防消毒が家族を守る鍵になります。ここでは0.02%の薄めの消毒液を使いましょう。
消毒すべきポイント
- トイレの便座・レバー・ドアノブ
- 洗面所の蛇口・ドアノブ
- 冷蔵庫や部屋のドアノブ
- テレビのリモコン
- 電気のスイッチ
- 階段の手すり
1日2回(朝・夜)、消毒液を染み込ませたペーパータオルで拭き取ります。スプレーではなく、拭き取り方式がウイルスを広げないコツなんですね。
金属部分は10分ほど置いた後、水拭きを忘れずに。腐食してしまうともったいないですから!
よくある失敗と注意点
実際の現場で見かける「やりがちな失敗」もお伝えしておきますね。
これはNG!
- アルコール消毒だけで済ませる ノロウイルスにはアルコールは効果が薄いんです
- 吐物にいきなり消毒液をスプレー ウイルスが飛び散る原因に。静かに拭き取るのが鉄則です
- 酸性洗剤と混ぜる 有毒ガスが発生して危険!トイレ用洗剤との併用は絶対NG
- 素手で処理 必ず手袋を!二次感染のリスクが高まります
- 消毒液の作り置き 効果が落ちるので、使う直前に作りましょう
小さいお子さんがいる家庭での注意
消毒液を入れたペットボトルは、飲み物と間違えないように「消毒液」とはっきり書いておきましょう。子どもの手の届かない場所に保管することも大切です。
また、症状が治まってからも1〜2週間は便からウイルスが出続けるそうです。油断せず、消毒は続けてくださいね。
脱水症状に注意!水分補給も大切
処理も大事ですが、本人のケアも忘れずに。激しい嘔吐や下痢が続くと、脱水症状が心配になりますよね。
少量ずつ、こまめに水分補給を。経口補水液やスポーツドリンク(薄めて)がおすすめです。一度に飲むと吐いてしまうので、スプーン1杯ずつから始めるのがコツですよ。
ぐったりしている、おしっこが出ない、唇が乾いているなどの症状があれば、早めに医療機関を受診してくださいね。
まとめ|慌てず、正しく、家族を守る
感染性胃腸炎の処理は、確かに大変です。でも、正しい方法を知っていれば、家族内での感染を防げる可能性がぐっと高まるんですね。
覚えておきたいポイント
- 吐物処理には0.1%、予防消毒には0.02%の塩素液
- 消毒液は使う直前に作る
- 汚れた衣類は下洗い→消毒→洗濯の順番で
- 換気と手洗いを徹底する
我が家では「吐物処理セット」を常備してから、夜中の突然の嘔吐にも落ち着いて対応できるようになりました。準備しておくと心に余裕が生まれますよ!
子育て中は、こういう「突然」がつきものです。でも、一つひとつ乗り越えていけば、きっと経験値になっていくはず。この記事が、そんな時の心強い味方になれたら嬉しいです!
参考資料
関連記事
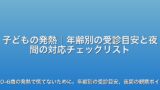
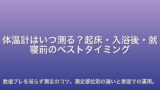
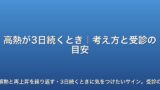
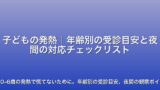
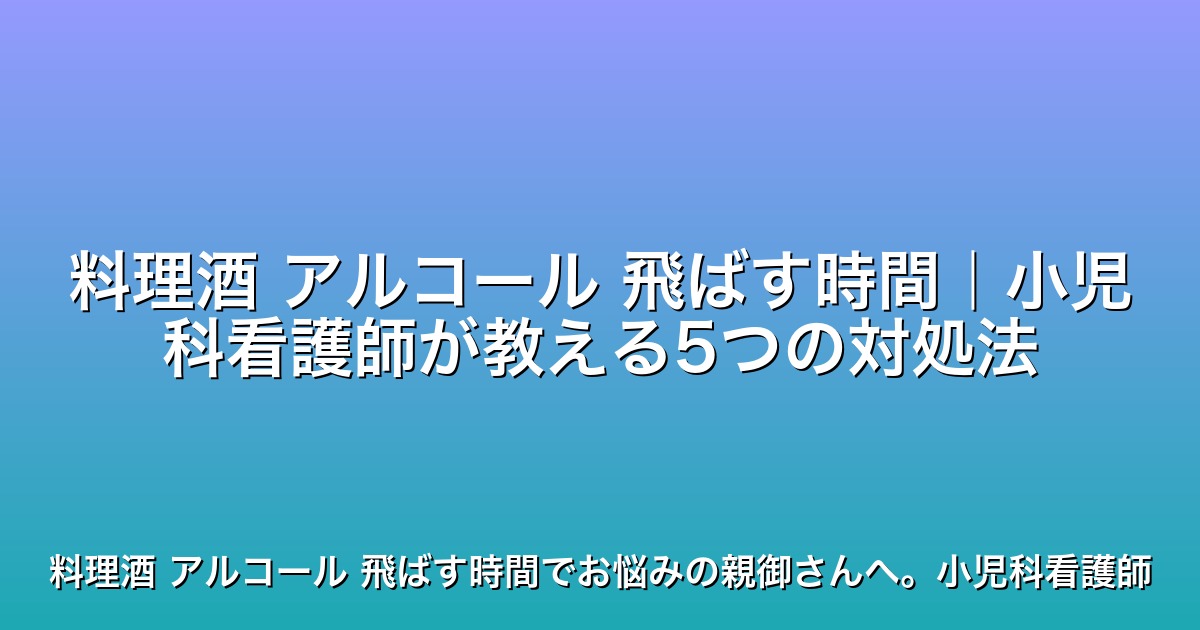
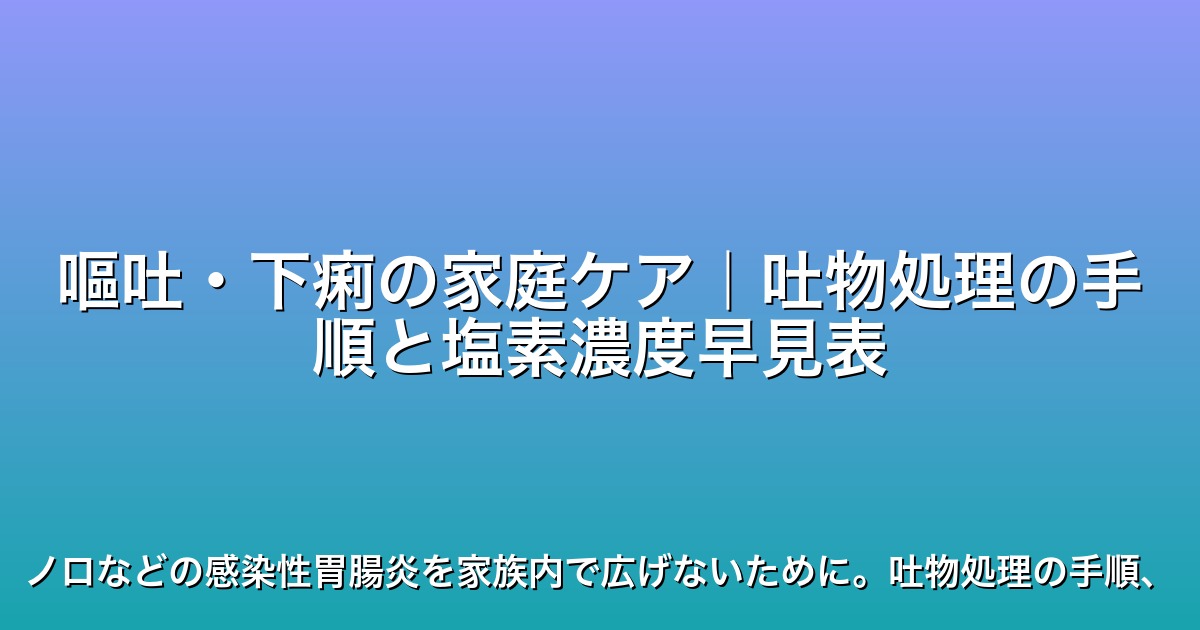

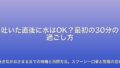
コメント