「昼間は元気なのに、夜になると咳がひどくなる…」というお子さん、意外と多いですよね。私自身も子育て中に何度も経験していて、夜中に咳き込む姿を見ると本当に心配になります。でも実は、夜に咳が強くなるのには理由があるんです!
今回は小児科看護師として、また親としての経験も交えながら、寝室の環境調整や枕の工夫について書いていきますね。少しの工夫で楽になることもあるので、ぜひ試してみてください。
なぜ夜になると咳がひどくなるの?
まず知っておきたいのが、夜間に咳が強くなるメカニズムです。昼間は元気だったのに夜だけ咳込むと「悪化してる?」と不安になりますが、実はこれ、体の自然な反応なんですよ。
夜になると副交感神経が優位になって、気管支が少し狭くなります。さらに横になることで鼻水や痰が喉に流れやすくなり、それが刺激になって咳が出やすくなるわけですね。加えて夜は気温が下がるので、冷たい空気が気管支を刺激することも。
つまり夜の咳は、必ずしも「病状が悪化している」わけではないんです。とはいえ、お子さん本人はつらいですし、咳で何度も目が覚めると睡眠不足になってしまいます。だからこそ、環境を整えてあげることが大切なんですね!
寝室環境を整える3つのポイント
咳を和らげるために、まず取り組みたいのが寝室の環境調整です。特別な道具がなくてもできることから始めましょう。
湿度を50〜60%に保つ
乾燥は咳の大敵です。空気が乾燥すると喉や気管支の粘膜が敏感になって、ちょっとした刺激でも咳が出やすくなります。理想的な湿度は50〜60%くらい。冬場の暖房が効いた部屋は特に乾燥しやすいので要注意ですよ!
加湿器があると便利ですが、ない場合は濡れたタオルを部屋に干すだけでも効果があります。我が家では洗濯物の部屋干しを寝室でしていた時期もありました。見た目はちょっとアレですけど、背に腹は代えられないですよね(笑)
加湿器を使う場合は、熱くならないタイプやお手入れしやすいものを選ぶと安心です。特に小さなお子さんがいるご家庭では、
が安全でおすすめですよ。カビが生えないよう、こまめなお手入れも忘れずに!
室温にも気を配る
体温と室温の差も咳の引き金になります。布団に入って体が温まると、その温度差で咳が出やすくなるんですね。寝室が寒すぎると冷たい空気が刺激になるので、適度に暖めておくのがポイントです。
ただし暖めすぎると乾燥がひどくなるので、加湿とセットで考えましょう。エアコンの設定温度は20度前後、布団や毛布で調整するイメージです。我が家では子どもが布団を蹴飛ばすので、寝室を少し暖かめにして薄手の布団にしていました!
寝る前の換気と空気の流れ
意外と見落としがちなのが空気の質です。ホコリやハウスダストが舞っていると、それが刺激になって咳が出ることもあります。寝る前に短時間でいいので窓を開けて換気しましょう。
また、布団や枕のホコリにも注意が必要です。布団を叩くとホコリが舞い上がるので、掃除機で吸い取る方が効果的ですよ。枕カバーやシーツはこまめに洗濯して、清潔を保ってあげてくださいね。
枕の高さと寝姿勢の工夫
環境を整えたら、次は寝る姿勢にも注目してみましょう。ちょっとした工夫で呼吸が楽になることがあります!
上体をやや高くする方法
完全に平らな状態よりも、上体を少し高くすると鼻水や痰が喉に流れ込みにくくなります。大人なら枕を高くすればいいのですが、お子さんの場合は首に負担がかからないよう注意が必要です。
おすすめなのは、布団やマットレスの頭側に薄いクッションやタオルを入れて、全体を緩やかな傾斜にする方法です。急な角度ではなく、ほんの少しだけ斜めにするイメージですね。枕だけを高くすると首がかくんと曲がってしまい、逆に気道が狭くなるので要注意!
赤ちゃんの場合は、抱っこした姿勢で寝かせてあげるのも効果的です。あごが上がった状態になるので気道が広がるんですよ。ただし腕は疲れますし、ずっと抱っこも大変なので、落ち着いたらそっと布団に下ろしてあげてください。
横向き寝も試してみて
仰向けよりも横向きに寝る方が、鼻水が喉に流れにくくなります。お子さんが嫌がらなければ、横向きの姿勢で寝かせてみるのもいいでしょう。ただし寝返りは自由にさせてあげてくださいね!
私の経験では、横向きで背中をさすってあげると安心して眠れることが多かったです。咳が出ているときは不安な気持ちになっているので、そばにいてあげるだけでも落ち着くみたいですよ。
そのほかに試せる対処法
環境と姿勢の調整に加えて、いくつか試せる対処法をご紹介します。すべてを一度にやる必要はないので、できそうなものから取り入れてみてください!
まず、寝る前に水分補給をしましょう。喉が潤うと咳が和らぐことがあります。常温か温かい飲み物がおすすめです。柑橘系のジュースは刺激になることがあるので避けた方が無難ですよ。
1歳以上のお子さんなら、寝る30分前にハチミツをひと匙なめさせるのも効果的です。ただし1歳未満の赤ちゃんには絶対に与えないでください。乳児ボツリヌス症のリスクがあって危険です!
夜中に咳き込んで目が覚めたときは、一度起こして水を飲ませてあげると落ち着くことが多いです。背中をトントンしたり、さすってあげるのも効果的ですね。
こんなときは受診を
環境を整えても咳がおさまらない、むしろひどくなっているという場合は医療機関を受診しましょう。特に注意したいサインをいくつか挙げておきますね。
咳と一緒にゼーゼー・ヒューヒューという音がする場合は、気管支喘息の可能性があります。肩で息をするほど苦しそうなときや、顔色が悪いときは早めの受診が必要です。夜間でも救急病院に連絡してください。
また、2週間以上咳が続く場合や、熱がないのに咳だけがずっと残っている場合も一度診てもらいましょう。単なる風邪ではなく、他の原因が隠れていることもあります。
生後3か月未満の赤ちゃんは特に注意が必要です。気管支が細くて痰を出す力も弱いので、咳の強さよりも哺乳ができているかどうかを見てあげてください。ミルクや母乳を飲めないようなら、すぐに受診しましょう。
夜間の咳は見ていてつらいですが、環境を整えることで楽になるケースも多いです。まずは湿度と室温、そして寝る姿勢を見直してみてください。それでも心配なときは、遠慮せず医療機関に相談してくださいね!
【内部リンク候補】
- 「子どもの咳が続くとき|受診の目安と家でできる観察ポイント」
- 「加湿器の選び方とお手入れ|子どもがいる家庭で気をつけること」
- 「夜泣きと咳の違い|赤ちゃんが夜中に目覚める理由を見極めるコツ」
- 「風邪のあとも咳だけ残る|感染後咳嗽について知っておきたいこと」
参考資料
- 子供の夜の咳がひどくなる原因|ちあふるクリニック東池袋小児科
- 子供の咳(夜だけ咳・痰がらみの咳など)|うつぼ本町キッズクリニック
- 子どもの咳がひどい時の受診の目安の症状・対処法|ひだまりこども診療所
- 子どもの咳が夜ひどくなる…寝れないときの対処法は? | キッズドクターマガジン
- 赤ちゃんがいるお部屋にも安心!加湿器の選び方のポイント | ダイニチ工業
関連記事
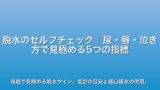
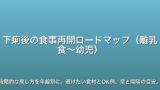
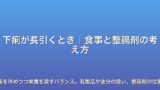
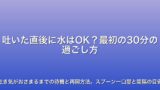
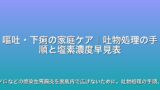
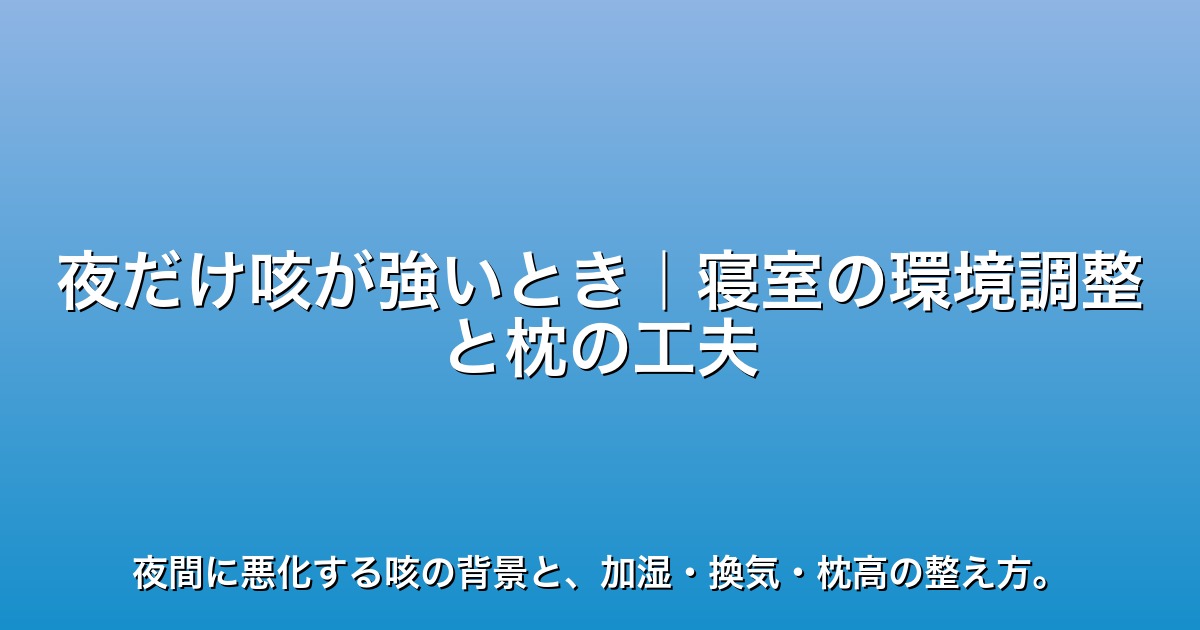

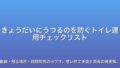

コメント