子どもの脱水、見逃していませんか?
小児科で働いていると、夏だけじゃなく冬の胃腸炎シーズンにも脱水で駆け込んでくる親子を本当によく見かけます。私自身も子育て中、わが子が下痢で丸一日おむつが濡れなかった時は心臓が凍りつきました!
子どもは大人より体の水分割合が高く(70〜80%)、代謝も活発なので脱水になりやすいんですね。でも早めに気づけば家庭での水分補給で十分回復できることが多いんです。今日は家庭で見極められる5つの脱水サインをご紹介します!
【チェック1】おしっこの量と回数
脱水を見極める一番わかりやすい指標がこれです。おむつが半日以上濡れていない場合、脱水が進んでいるサインと考えられます。いつもは2〜3時間おきにおむつ交換しているのに、気づいたら6時間以上乾いたまま…なんてことありませんか?
また、尿の色が普段より濃くなっている場合も要注意です。健康な時は薄い黄色なのに、オレンジっぽい濃い色になっていたら体が水分不足のサインを出しているわけです。おむつ替えの時に色をチェックする習慣をつけておくといいでしょう!
おしっこチェックのコツ
- おむつ替えの時刻をメモしておくと間隔がわかりやすい
- スマホのアプリで記録すると便利です
- 濃い色のおしっこは写真に残しておくと受診時の説明に役立ちます
【チェック2】唇と口の中の状態
唇がカサカサに乾燥していたり、口の中が乾いている場合は脱水の可能性があります。普段はぷるぷるの赤ちゃんの唇が、白っぽくひび割れているとドキッとしますよね。
さらに確認したいのがよだれの量です。普段よりよだれが少なくなっている時も注意が必要でしょう。いつもはスタイがびしょびしょになるのに、妙に乾いている…そんな時は他のサインも合わせてチェックしてみてください!
【チェック3】泣いても涙が出ない
これは私が小児科で最も重視する観察ポイントの一つです。機嫌が悪くて泣いているのに涙が出ていない、または涙の量が明らかに少ない場合、脱水のサインと考えられます。
健康な時は「ワーン!」と泣けば涙がポロポロ出るのに、声を出して泣いているのに目が乾いている…そんな時は要注意なわけです。ただし月齢の低い赤ちゃんはもともと涙腺が未発達なので、3ヶ月以降で比較してみるといいでしょう。
【チェック4】皮膚と脇の下の乾燥
手の甲の皮膚を軽くつまんでみて、元に戻るのに2秒以上かかると脱水の可能性があります。これは「皮膚ツルゴール」という医療用語で呼ばれる観察方法なんです。健康な時はすぐにパッと戻るのに、脱水が進むとゆっくり戻るんですね。
また、脇の下を触ってみて乾燥している場合も脱水のサインでしょう。通常は汗で少し湿っているものですが、脱水になると汗をかかなくなって乾いてしまうわけです。お風呂上がりや授乳の時など、自然に触れるタイミングで確認してみてください!
簡単セルフチェック方法
- 手の甲の皮膚を優しくつまんで2秒以上かかるか確認
- 脇の下を触って湿り気があるかチェック
- お腹の皮膚も同じ要領で確認できます
【チェック5】元気と機嫌の変化
いつもより元気がなくぐったりしている、または機嫌が悪く不機嫌が続く場合、脱水が進んでいる可能性があります。これは数値で測れないからこそ、普段の様子を知っている親御さんの観察が本当に大切なんです!
うちの子も胃腸炎の時、いつもならおもちゃに飛びつくのに横になったまま動かなくて…その時初めて「これは様子がおかしい」と気づきました。「なんとなくいつもと違う」という親の直感、侮れないんですよ。
家庭でできる水分補給の方法
脱水のサインに気づいたら、まずは落ち着いて水分補給を始めましょう。嘔吐がある場合は少量ずつ約10分おきに与えるのがポイントです。一気に飲ませるとまた吐いてしまうことがあるんですね。
スプーン1杯から始めて、吐かないようなら徐々に量を増やしていきます。ここで活躍するのが経口補水液です!
は水分だけでなく電解質(ナトリウムやカリウム)も補給できるので、脱水時には最適なんですよ。
経口補水液が飲めない時の工夫
- 凍らせてシャーベット状にすると食べやすくなります
- 少し温めるとにおいが和らいで飲みやすくなることも
- ストローやスポイトを使うと少量ずつあげられて便利です
- 母乳やミルクの赤ちゃんはそのまま継続できます
こんな時はすぐ受診を!
家庭での水分補給を試みても、以下のような状態が見られる場合は迷わず医療機関を受診してください。これは看護師として強調しておきたいポイントです!
- うとうとして呼びかけへの反応が鈍い(嗜眠状態)
- けいれんを起こしている
- 呼吸が速く苦しそう
- 経口補水液を全く受け付けず、何度も吐いてしまう
- 手足が冷たくなっている
- 赤ちゃんの場合、大泉門(頭のてっぺんの柔らかい部分)が凹んでいる
特に3ヶ月未満の赤ちゃんは急速に悪化することがあるので、迷ったら受診するのが安全でしょう。夜間や休日でも救急外来を利用してかまいません!
脱水を予防する日常の工夫
脱水は予防が何より大切です。普段から意識的に水分を取る習慣をつけておくといいですね。特に夏場や暖房の効いた冬の室内では気づかないうちに水分が失われているんです。
日常でできる予防策
- 起床後、遊びの後、お風呂上がりなど定期的に水分補給のタイミングを作る
- 外出時は必ず水筒を持参する習慣を
- 発熱や下痢の初期から小まめに水分を与える
- 室温と湿度を適切に保つ(冬は加湿も忘れずに!)
- 普段から子どもの尿の色や回数を観察しておく
まとめ:観察と早めの対応がカギ
脱水の5つのサイン、覚えていただけましたか? おしっこの量、唇の乾燥、涙の量、皮膚の状態、元気の様子。この5つをチェックすれば、家庭でもかなり正確に脱水の程度を判断できると思います。
小児科で働いていて思うのは、「早めに気づいて対処できた」ケースがほとんどだということ。親御さんの「なんかおかしい」という直感と日々の観察が、子どもを守る最大の武器なんですね。不安な時は遠慮せず小児科に相談してください。私たちはいつでも味方ですよ!
この記事が、皆さんの子育ての不安を少しでも和らげるお役に立てれば嬉しいです。一緒に乗り越えていきましょう!
参考資料
- 小児の脱水 – MSDマニュアル家庭版
- 子供の脱水症状を見分けるポイント – 長尾台診療所
- 子どもの脱水症のサインは? – キッズドクターマガジン
- とっさの家庭看護 – 埼玉県立小児医療センター
- 【医師解説】赤ちゃんの脱水症状に気をつけよう
関連記事
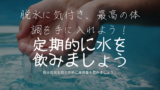
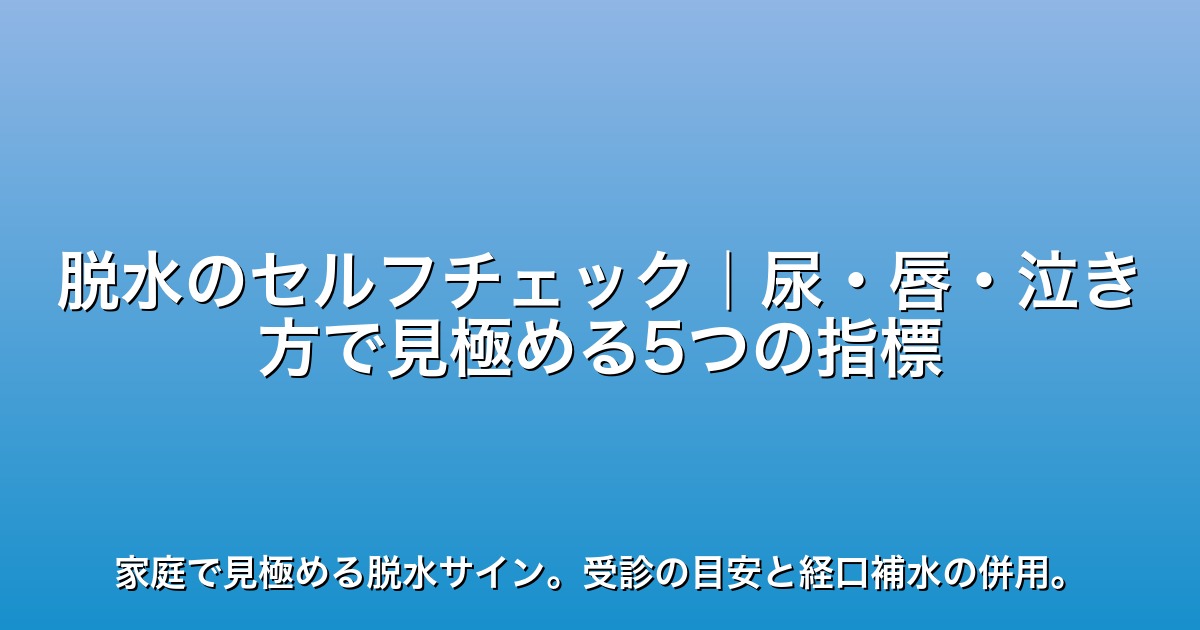

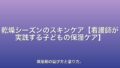
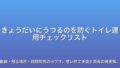
コメント