夜中に子どもの体が熱い!そんなとき、すぐに病院に行くべきか迷いますよね。私も小児科看護師として働きながら子育てをしていますが、初めて我が子が高熱を出したときは本当に焦りました。
今回は、年齢別の受診目安と夜間にチェックすべきポイントを具体的にお伝えします。印刷して冷蔵庫に貼っておける実用的な内容になっていますよ!
発熱の基礎知識|何度から「熱」なの?
まず知っておきたいのは、子どもの平熱は大人より高めだということ。乳幼児の場合、37.5℃までは平熱の範囲内と考えられています。小児科では37℃台後半を「微熱」、38℃以上を「発熱」と表現することが多いですね。
新生児の平熱は平均37.1℃とされていて、大人より0.5℃ほど高いんです。「いつも37℃ちょっとある…」というのは実は正常なわけです!
重要なのは「熱の高さ」ではなく「子どもの様子」。38℃台でも元気に遊んでいる子もいれば、37.5℃でもぐったりしている子もいます。体温計の数字だけでなく、全体的な状態を見ることが大切だと思います。
【年齢別】受診の目安をチェック
生後3ヶ月未満の赤ちゃん
この時期の発熱は特に注意が必要です。38℃以上の発熱があれば、たとえ元気そうに見えても速やかに受診してください。抵抗力が未熟なため、重症化する可能性があるんです。
夜間でも迷わず受診を。多くの小児科医が「生後3ヶ月未満の38℃以上は原則として入院管理」と考えています。
生後3ヶ月~6歳
この年齢になると、熱の高さよりも「全身状態」が判断のポイントになります。以下のいずれかに当てはまる場合は、夜間でもすぐに受診しましょう。
- 顔色が悪く、ぐったりして元気がない
- 呼吸が苦しそう、肩で大きく息をしている
- 水分が全く取れない、おしっこが半日以上出ていない
- けいれん(ひきつけ)を起こした
- 泣き方がいつもと違う(弱々しい、または激しく泣き続ける)
- 嘔吐や下痢を繰り返している
逆に、38℃以上の熱があっても水分が取れて機嫌もまあまあなら、翌朝の受診でも大丈夫なことが多いです。ただし、発熱が3日以上続く場合は、全身状態が良好でも受診をおすすめします。
夜間の観察ポイント|これだけはチェック!
夜中に子どもが発熱したとき、どこを見ればいいのか。小児科勤務で学んだチェックポイントをまとめます。
水分摂取の確認
発熱時は汗をかくため脱水になりやすいです。少量ずつでも水分が取れているか、おしっこの回数や色をチェックしましょう。おしっこが濃い黄色になっていたら要注意のサインです。
呼吸の様子
「ハアハア」と苦しそうに呼吸していないか、胸やお腹が大きく上下していないかを見ます。呼吸が速すぎたり、喉がヒューヒュー鳴っていたりする場合は早めの受診が必要でしょう。
意識レベル
呼びかけに対する反応が鈍い、目の焦点が合わない、ぼんやりしているといった様子があれば要注意。高熱でぼーっとしていても、解熱剤で熱が下がったときに普段の様子に戻るなら心配しすぎなくても大丈夫なことが多いです。
体温測定のコツ
正確に体温を測るために、脇の下をしっかり拭いてから測定します。動き回る子には非接触体温計が便利ですね。おでこにかざすだけで1秒程度で測れるタイプなら、寝ている間にも測定できます。
我が家でも夜間の体温チェックには非接触タイプを使っていますが、バックライト付きで暗い部屋でも見やすく、測定音をオフにできるものが本当に助かっています。
解熱剤の使い方|タイミングと注意点
「熱が出たらすぐに解熱剤!」と思いがちですが、実はそうでもないんです。解熱剤は「熱を下げる」というより「しんどさを和らげる」ためのお薬だと考えてください。
解熱剤を使う目安
- 38.5℃以上で本人がしんどそう
- 痛みや倦怠感で水分が取れない
- 眠れない、泣き続けている
- 咳がひどく呼吸が苦しそう
元気があって水分も取れているなら、無理に熱を下げる必要はありません。発熱は体が病原体と戦っている証拠でもあるんです。
アセトアミノフェンの使い方
小児科で主に処方されるのはアセトアミノフェン(カロナール、アンヒバ、アルピニーなど)です。内服薬は飲んでから30分ほどで効き始め、4時間程度効果が持続します。
座薬と内服薬は成分が同じなので、効果も同じ。使用間隔は6~8時間空けるのが基本です。体重に合わせた量が処方されているので、他の子のものを使い回したりしないでくださいね。
困ったときは#8000へ相談を
夜間に「受診すべきか様子を見るべきか」迷ったら、小児救急電話相談(#8000)に電話してみてください。休日・夜間に小児科医や看護師が電話で相談に乗ってくれる無料のサービスです。
プッシュ回線や携帯電話から「#8000」をダイヤルすると、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されます。実施時間は自治体によって異なりますが、多くの地域で19時~翌朝8時まで対応しています。
「こんなことで電話していいのかな」と遠慮せず、心配なことがあれば気軽に相談してみましょう。私も何度もお世話になっていますよ!
家庭でできるケアのポイント
適度な室温と衣服
熱の出始めで寒がっているときは1枚多く着せて温めます。熱が上がりきって暑がるようになったら、厚着を避けて涼しくしてあげましょう。こまめな着替えも大切です。
水分補給を最優先に
食欲がなくても水分さえ取れていれば大丈夫。湯冷まし、麦茶、経口補水液、薄めたりんごジュースなど、飲めるものを少しずつ与えます。アイスクリームやゼリーも水分補給になりますよ。
固形物を食べさせることが難しければ、プリンやヨーグルトから始めてみてください。消化に良い具沢山のお味噌汁やスープは、栄養も塩分も一緒に摂れるので理想的ですね。
入浴について
「熱があるときはお風呂に入っちゃダメ」と言われたことがあるかもしれませんが、実は医学的根拠はないんです。ぐったりしていなければ、シャワーや入浴で汗を流して清潔に保ってあげても問題ありません。
【印刷用】夜間受診チェックリスト
以下の項目に1つでも当てはまれば夜間でもすぐに受診を検討してください。
- □ 生後3ヶ月未満で38℃以上の発熱
- □ 顔色が悪く、ぐったりしている
- □ 呼吸が苦しそう、肩で息をしている
- □ けいれん(ひきつけ)を起こした
- □ 呼びかけに反応が鈍い、意識がもうろうとしている
- □ 水分が全く取れない
- □ おしっこが半日以上出ていない
- □ 嘔吐や下痢を激しく繰り返す
- □ 泣き方が異常(弱々しい/激しく泣き続ける)
- □ くちびるや爪が紫色になっている
上記に当てはまらなくても、「いつもと違う」「なんだか様子がおかしい」と感じたら、迷わず医療機関や#8000に相談してください。親の直感は意外と当たるものです。
さいごに
子どもの発熱、本当に心配になりますよね。でも多くの場合、発熱は体が病気と戦っている正常な反応なんです。熱の数字に一喜一憂するより、子どもの全体的な様子を見ることが大切だと思います。
「これくらいで受診していいのかな」と迷ったときは、遠慮せずに相談してください。かかりつけの小児科や#8000、夜間救急外来、みんなが子育てを応援していますよ。
一緒に乗り越えていきましょうね!
参考資料
関連記事
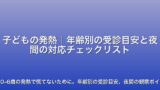
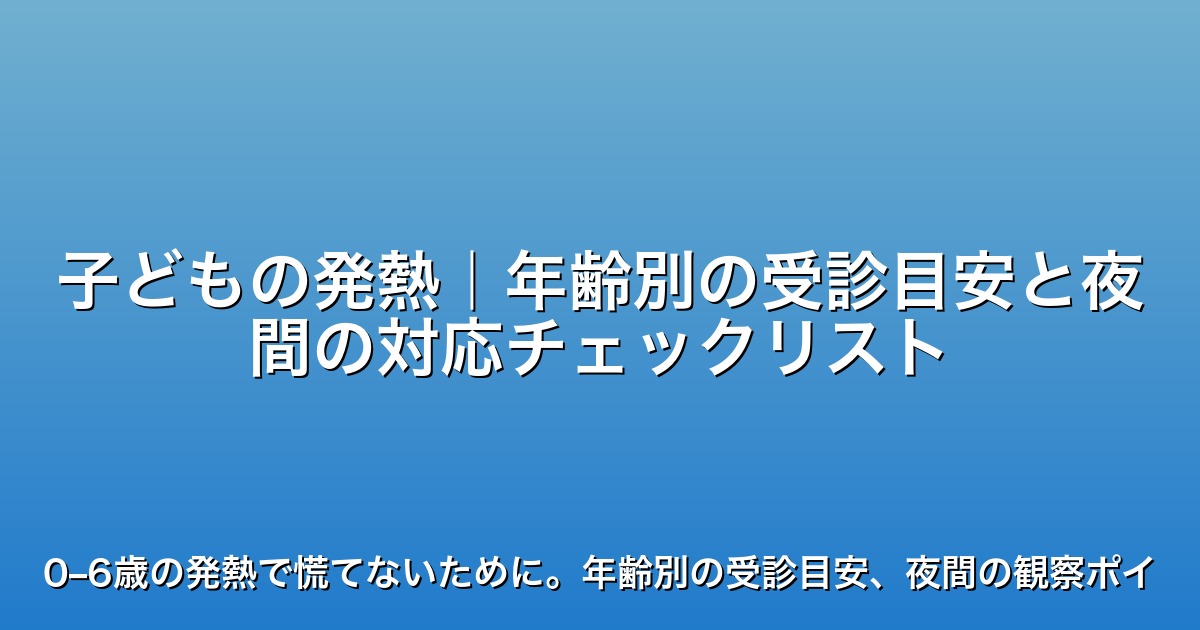
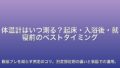

コメント